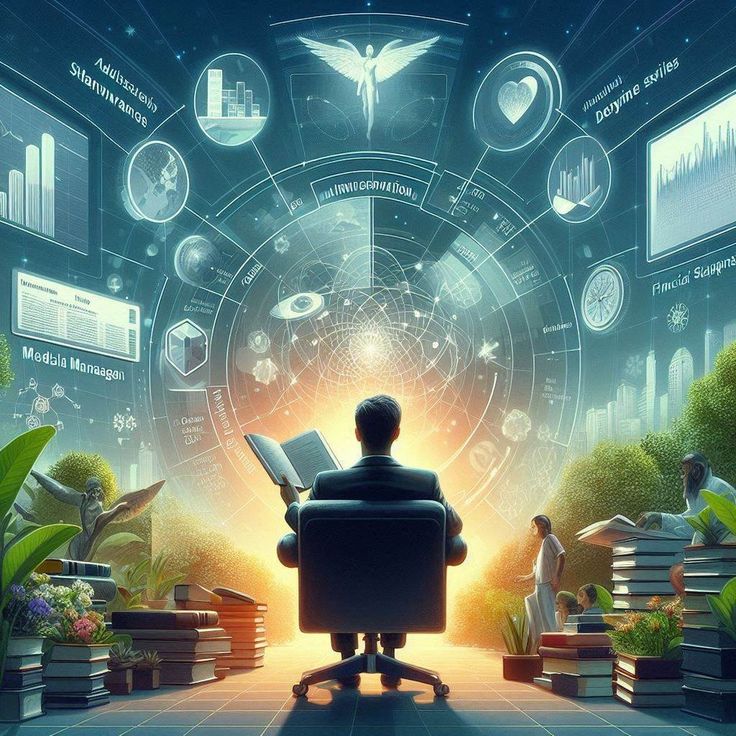
皆様、こんにちは。LIFE行政書士事務所の中江です。
3連休の初日の土曜日雨が凄かったですね!
今年は梅雨があまりなかったので、妙な天候の日が多い気がします。
これから花火大会とか色々イベントがありますので、大切な日は天気が崩れないといいですね。
では、ブログを書きます。
前回から「遺言執行者」の記事を書いてます。
遺言執行者のお仕事の流れはざっくりとこうなります。
①お亡くなりになったことを知った後に、相続人全員に遺言執行者に就職したことを、通知する。(民法第1007条)
②遺言書の内容通りに手続きを行う。
③完了したら完了報告をする。(民法第654条、民法第655条、民法第1020条)

今回は②遺言書の内容通りに手続きを行うの辺りを書きます。
遺言書の場合、書き方は様々ですが、不動産と金融機関が多くの割合を占めるので、今回はこの2つを中心に書きたいと思います。
まずは不動産です。
相続法が改正される前は、特定の相続人に不動産を承継される内容の遺言があった場合は、遺言執行者は登記手続きが出来ず、相続人が登記手続きをすることとされてました。
民法上「特定財産承継遺言」と呼ばれています。
現在は、相続法が改正され、民法第1014条で、遺言執行者が手続ができる旨が記載されてます。
こちらは、預貯金債権も同様です。
ですので、不動産の相続登記の際に発生する登録免許税を確定させるため、
①市役所で名寄帳を取得し、最新の不動産の評価額を確認します。
②その後、法務局で不動産の登記簿謄本を取得し、不動産の相続登記を行います。
相続の時は遺産分割証明書等が必要ですが、遺言ですので、公正証書遺言を提出したりします。
丁寧に法務局の職員さんが教えてくれるので、リラックスして申請に行かれていいと思います。

次に金融機関です。
預貯金債権、有価証券など様々ですが、こちらも遺言執行者であることを明らかにするための本人確認書類や、公正証書遺言の正本を提出したりします。
実印で手続きを行うことが多いので、印鑑証明書も準備しますが、金融機関によっては、有効期間が半年以内、3か月以内とバラバラなので、先に確認をした方がいいです。
割と多い、ゆうちょ銀行等もwebで先に登録しておくと、ゆうちょ銀行に行く回数を1回減らせたりするので、先にお電話で段取りを確認しておくと楽になります。
割と最近始まったNISAとは、手続が煩雑で時間が凄くかかるので、あらかじめそのつもりでいた方がいいと思います。
有価証券も結構時間と手間がかかります。
金融機関から発行される書面は全てきちんと保管をお願いします。

基本的に銀行の行員さんはみんな優しいので、分からないことがあればお気軽に聞いていただいても問題ないかと思われます。
今回書いた内容が、実際に遺言書の内容通りに手続きを行う詳細です。
ポイントとしては、チープな表現になって申し訳ございませんが、「色々聞きながらやる」です。
法務局も金融機関も割と細かく教えてくれます。
私も聞いたことがない県外の金融機関の手続きをする時も相当電話して確認しながら聞きますが、本当に親切に対応して下さるので、本当に助かってます。

では、次回が最終回、③完了したら完了報告をする。(民法第654条、民法第655条、民法第1020条)を書きますので、宜しくお願い致します。
今回も読んで下さり、有難うございます。






