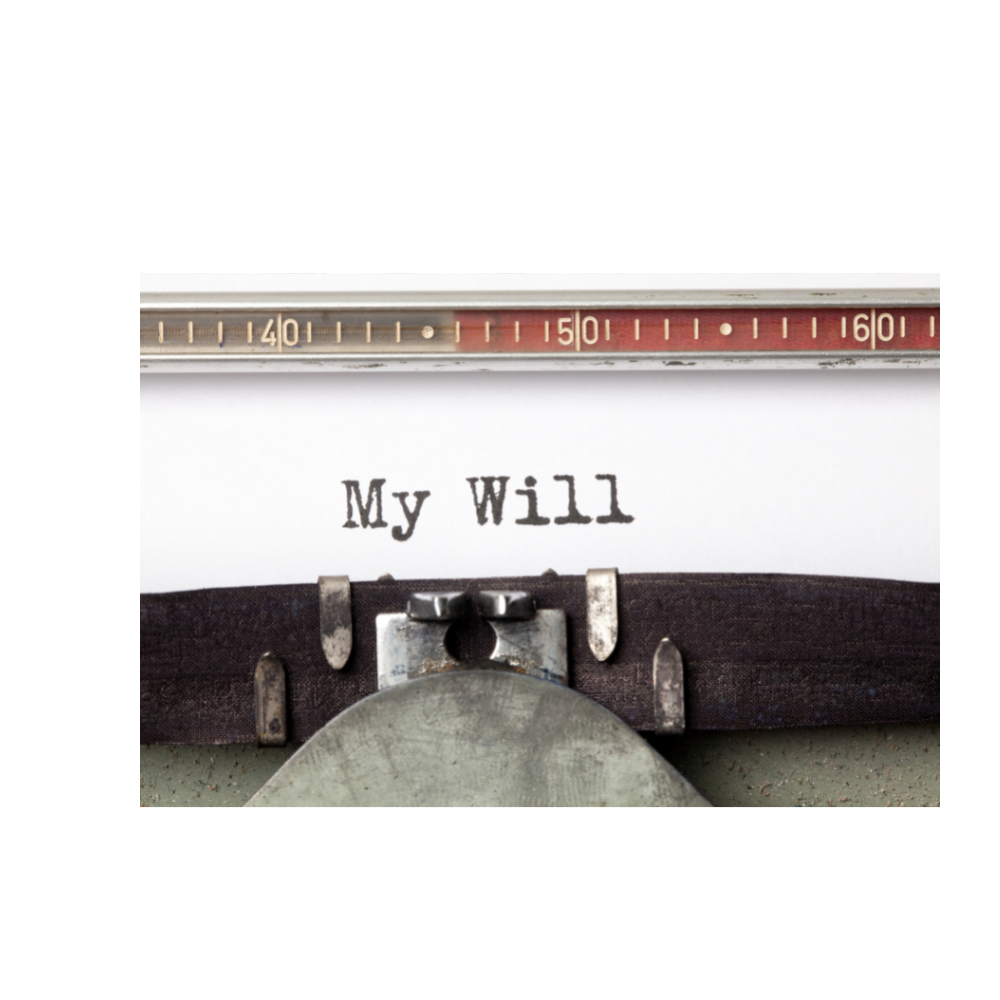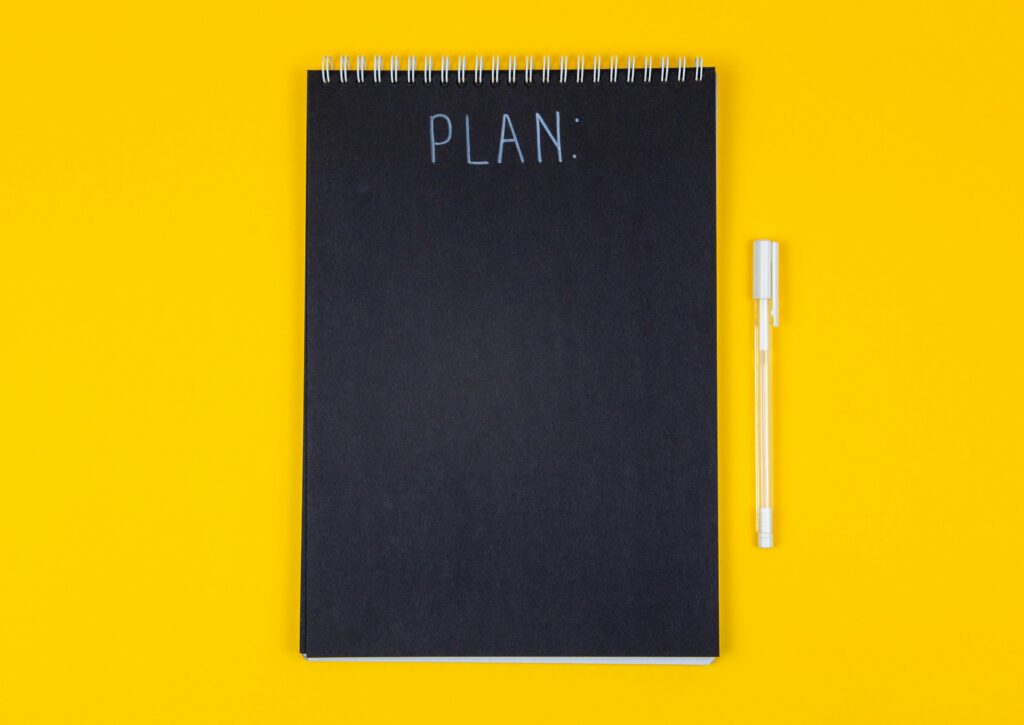
皆様、こんにちは。LIFE行政書士事務所の中江です。
ちょっとバタバタしていてブログを書くのが少し遅れました。
もうすっかりお盆ですね。
今回は最大9連休の会社も多いみたいですが、皆様どのようにお過ごしですか?
久々の帰省もいいもんですね。
弊所は相変わらず、今年のお盆も通常営業で日曜日のみの休みですので、帰省はしてないです。
来年こそはと思っております。
では、ブログを書きます。
前回から「遺言執行者」の記事を書いてます。
遺言執行者のお仕事の流れはざっくりとこうなります。
①お亡くなりになったことを知った後に、相続人全員に遺言執行者に就職したことを、通知する。(民法第1007条)
②遺言書の内容通りに手続きを行う。
③完了したら完了報告をする。(民法第654条、民法第645条、民法第1020条)

今回は③完了したら完了報告をする。(民法第654条、民法第655条、民法第1020条)を書きます。
基本的に遺言執行の実務の初めから終わりは民法の中で明記されている内容が多いです。
完了報告もその一つです。
完了報告は一般的に完了報告書を作成し、相続人に郵送することがほとんどです。
書面できちんと形に残しておいた方が、万が一の未来の争いを防ぐことに繋がります。
特に決まったフォーマットもないので、「どの財産を、いつ、どのように処分した」かが、分かれば大丈夫だと思います。
インターネット上にもひな形が転がっているみたいだったので、ご参考にされてよいかと思います。
民法第1020条は、民法第654条の委任の終了後の処分と、民法第655条の委任の終了の対抗要件を準用しています。
完了報告は速やかに行う必要があります。
遺言執行者は、その任務の終了事由を通知することがどうしても必要であり、通知するまでは遺言執行者はその任務の終了を対抗ないからです。
相続人の皆様が知らないところで動いているので、速やかに通知することで、不測の損害を予防することも出来るためです。
以上で、遺言執行者のお仕事は終了となります。

今回、何回かに分けて、遺言執行者のお仕事を、さらっと書きましたが、実務はなかなか煩雑です。
時に相続人から激しい当たりを受けることもあります。
ですが、就職したからには、(就職しないこともできます)責任を持って、最後までやり遂げるお仕事です。
実務のナビゲーションは全て民法という法律の中にありますが、もし困ったことがあったら、いつでもご相談下さい。
遺言執行者の復代理人として動くことも結構ございますので。
そもそも「執行者」の言葉の意味は、ある計画を実行したり、義務や責任を果たすために行動する人のことを指します。
そう考えると、遺言を残すこと、これが「計画」であり、それを実行するのが、遺言執行者。
実行する執行者には義務と責任が発生することになります。
すべては、遺言を残し、他界した、あの人のために。
ですので、無機質に静かに動きます。
それが執行するということです。
今回も読んで下さり、有難うございました。
またブログを書きますので、宜しくお願い致します。